

おりがみ庵
岡村昌夫
女もすなる折り紙といふものを男もして見んとて、つれづれなるままにもてあそびたる、いそのかみ古き紙々、もみぢばの塵とつもれど、人の見るべきものにもあらねば、やがて武蔵野の煙りともなりなんを、あし引きの山口の君の企画によりて、ここにかつがつ筆を染むるものならし。春の日の至り至らぬところはあれど、これを読みたまふ人々、寛き御心もて許したまへかし。平成ふたつなる午の年の暮、
おりがみ庵主人敬白
【 第一回 】
個人的なことだが1990年は鶴に明け鶴に暮れてしまった。『千羽鶴折形』を2セット以上折ったから、1羽1000年としてどれくらい寿命が延びたか計算もしきれない。
考えて見ると、私が初めて折り鶴を作ってから半世紀以上過ぎた今日の日まで、どれほどの数の鶴を折ってきたのか全く見当もつかないが、他の折り紙と比べて折った回数が飛び抜けて多いことだけは確かである。その間の『千羽鶴折形』との出会いを含めていささかの感慨無しとしないのは年を取ったしるしであろうか。
私が通っていた麻布の南山幼稚園は、当時創設されたばかりの公立幼稚園だが、特にお世話になった小山田先生は、現在でもさっぱり年令不詳のエネルギッシュな先生である。ある時珍しく欠勤されたことがあった。幼い私はわざわざ門のところへ行って外を覗き、「おや、まだ先生来ないよ。」と独りごちた。これは私の駄じゃれの言い初めで、言葉に興味を持ったという点で、自分史上欠かせない出来事であるが、もう一つの欠かせない出来事もそのころのことであった。小山田先生から教えて頂いた鶴の折り方の件である。
それまでは普通に三角に二度折ってからつぶす方法で折っていたが、幼稚園では、まず長方形に折った。つまりNOAテキストの第二の折り方である。これを教えられた時の喜びは忘れられない。まるで魔法の折り方であった。
その後、いつのころからか、山線谷線をつけておいてから畳むNOAテキスト第三の方法も考え出していたが、『千羽鶴折形』を折るようになってから大きな疑問に突き当たってしまうことになる。
第一の、伝承の折り方だけで『千羽鶴折形』を折るのは極めて困難である。現在ではヘラで全部の筋をつけておいてから折る人もいるが、挿絵で見るかぎり当時の人はハサミ以外の道具を使っていない。魯縞庵はどうやって折っていたのだろうか。
その疑問を解く鍵は最近やっと発見した。「かやら草」の蟹の折り図をよくよく見ると、筋の脇に「内」「外」と書いてある。これは谷線・山線のことであろう。この筋をしっかり付けておいて畳めという指示もある。つまり第三の方法で一度に四つの正方基本形を折っていたのである。これなら「蓬莱」や「竜胆車」で私が新しいと思って折っている方法と同じではないか。
【第二回】
前回で少し触れた『かやら草』の「蟹」および「蜘くも」の折り図では、実線の脇に「外」と書いて「山線」を、点線の脇に「内」と書いて「谷線」を表している。
『かやら草』では、この他にも面白い山線と谷線の表記法があるので紹介しておこう。「おびな」と、六歌仙の「業平」「文屋」「黒主」の展開図をよく見ると、折り順を示す番号の一部が、裏文字(鏡文字)になっている。他は番号順に山折りしてゆくが、ここだけは谷折りせよという指示になっているのだ。右の図は「業平」の部分だが、「十」の鏡文字と判らせるために筆の勢いを使っているところなど感激ものである。従来折り紙愛好家の手元に流布している『かやら草』のコピーは主としてアメリカ版(写本)であって、それだと写した人が理解出来なかったらしく普通の文字に書き直してあるので、折り紙専門家の先生がたもあまりお気付きではないようだ。粗雑な写本とは似ても似つかぬ美しい原本がまだ出版されていないという折り紙後進国日本の現状がなげかわしい。(原本の一部がモノクロで佐久間女史の本の付録にあるだけだ。)
『かやら草』は1845年までに書かれた本だが、それより古い「福助折形工夫の伝」(1806年)にもはっきりと山と谷の区別が示されている。展開図が太線と細線で書かれていて、「ふと筋はそとへ、ほそハ内へ折」と説明されている。線種によって山谷を書き分けている資料としてはこれが現存最古のものであろう。『秘伝千羽鶴折形』(1797年)が山谷の区別を全く表現しようともしていなかったのに比べて、画期的な進歩があったわけだ。
『秘伝千羽鶴折形』より古いと思われる『折形手本忠臣蔵』は、「上へ折」「下へ折」「うらへ折」などと書いて説明しているが、中割折りを「内へ折り込」と説明しているのが注目される。
以上、山谷区別の表記法だけでも各種あって、折り方が似てはいるがいくつもの流派があったことを推測させる。何人もの「先生」(男性らしい)が、換骨奪胎、工夫を重ねてきたのだろう。これらすべてが魯縞庵義道の作などとはとても考えられない。
【第三回】
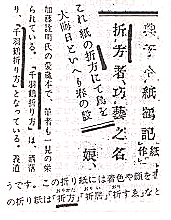 本新聞の「編集人」としての立場から一言お詫びを申し上げるが、前号にはミスプリントが多々あり、汗顔のいたりである。校正の手抜きであったが、中でも『千羽鶴折方』などを見過ごしたのは(*)遺憾であった。
本新聞の「編集人」としての立場から一言お詫びを申し上げるが、前号にはミスプリントが多々あり、汗顔のいたりである。校正の手抜きであったが、中でも『千羽鶴折方』などを見過ごしたのは(*)遺憾であった。
言い訳ではないが、実は「折形」を「折方」と書くミスは江戸時代から現代に至るまでさかんに繰り返されているので、(右のコピーはミスの例の一部である。書名はいちいちあげない。)今回はその「意味」を考えてみることにする。(転んでもただでは起きない。)
「折形」を「折方」と書き誤ったり、ミスプリントされたりしがちなのはなぜであろうか。最近の特殊な事情としては、ワープロに「折形」が登録されていないための漢字変換ミスが有り得る。それでも普通には「折り方」と出る筈だから、わざわざ「り」を抹消しなければならない。それでも気がつかないのはなぜだろうか。勿論、書き手が漢字に疎いためではあるまい。その証拠に、江戸時代の偉い漢学の先生が書き間違えている例をお示ししよう。
『秘伝千羽鶴折形』の折形考案者、魯縞庵義道の折り紙の業績を称えた貴重な文献として「紙鶴記」という漢文が知られている。桑名藩に仕えた儒者で、広瀬蒙斎という先生が書いたものであるが、その書き出しの部分が「折方者、巧藝之名也」(折り方は、巧芸の名なり)となっているのである。これは「折形」でなければならないところであろう。
なぜこういうミスが起きるのか。答えは二つ。まず「折形」という語が、漢文の大先生や現代人に定着していない語彙であること。さらに、両語の「発音」が同じであること。アクセントは別にして、江戸時代から現代まで「折形」が「おりがた」ではなく「おりかた」であったということである。『千羽鶴折形』を紹介した多くの英文の本がSenbazuru-orikataと書いてorigataとしなかったのは正しかったのだ。ピーター・エンゲルさんが“How to Fold One Thausand Cranes”と誤訳した話を前に書いたが、同情すべき事情はあったのである。
(*(編集部注):探偵団新聞第7号のある記事で「千羽鶴折方」という誤字がありました。「おりがみ庵」ではありません)
【第四回】
『秘伝千羽鶴折形』(1797年刊)についての宣伝文句に「世界最古の折紙の本」と書かれることが多い。私の出品した世界の折紙展のコーナーにもそう書いてあった。勿論これは誤りではない。しかし必ずしも正確とは言い難いところがあるのである。
もし出来るだけ正確に表現するならば、「現存することが確認されている、世界最古の、遊戯折紙を中心素材とした、本の形をした出版物」とでも書かなければならない。
儀礼折紙ならば伊勢貞丈の「包之記」(1764年)の方が古いし、本の一部に折鶴などが出て来るだけなら幾つか古いものがある。去年のシンポジウムで吉田正美先生が発表されたように、『秘伝千羽鶴折形』より七年も早い寛政二年の『大坂書林板木目録』に、既に『忠臣蔵折形』が出ているが、これは「本」ではない刷り物であるし、また同目録にある『智恵折形工夫之傳』は現存することが確認されていない。
それに『秘伝千羽鶴折形』という本は、折紙をネタにした狂歌本なのか、狂歌本の形をとった折紙の本なのか、ということも一応考えるべきだろう。題名や序文などからは、折紙の紹介を主眼としている本と解釈して良かろうと思われるが。
そんなわけで「世界最古の・・・」と書かれるたびに、誤りというわけではなくても、内心ドキドキしてしまうのである。
驚いたのは今年の正月、千羽鶴展をやったとき、某夕刊新聞に載った紹介記事に「2000年前の折紙の本」と書かれてしまったことだ。勿論「200年前」のミスだが、紙の発明以前から折紙があったということに記者氏は疑問を待たなかったのだろうか。もっとも、この新聞の記事を見て展示を見に来たというお客はいなかったようなので、読者がどう判断したかは不明である。そう言えば、雑誌『おりがみ』187号に広告が載っていた某書によると、折紙の起源は紙の無かった古代の神事に逆上ることになるが、この書物には、内容を他人に漏らしたら祟りがあっても知らないぞという趣旨の断り書きが付いているので、残念ながらこれ以上書くわけにはいかない。
【第五回】
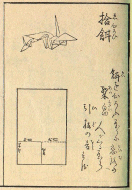 『秘伝千羽鶴折形』という本は、この十数年の間に、折り紙ファン層の中に深く静かに浸透していた。一人でこつこつ折る少年がいるかと思えば、千羽鶴折形研究会を作って研鑽を重ねる熟年者のグループがあったり、その年令性別を問わぬ広がりぶりを考えると、ここにこそ折り紙の魅力とは何かという問題の鍵を見る気持ちがするのである。
ところで、『千羽鶴折形』は、数々の誤解に取り囲まれた不幸な運命の書でもあった。今回のNOAブックスの解説書は、その誤解を少しでも晴らしたいという筆者たちの情熱の表れだったことを多くの読者の皆さんに理解して頂きたい。その意味もあって、本稿も当分『秘伝千羽鶴折形』に集中することになる。
『秘伝千羽鶴折形』という本は、この十数年の間に、折り紙ファン層の中に深く静かに浸透していた。一人でこつこつ折る少年がいるかと思えば、千羽鶴折形研究会を作って研鑽を重ねる熟年者のグループがあったり、その年令性別を問わぬ広がりぶりを考えると、ここにこそ折り紙の魅力とは何かという問題の鍵を見る気持ちがするのである。
ところで、『千羽鶴折形』は、数々の誤解に取り囲まれた不幸な運命の書でもあった。今回のNOAブックスの解説書は、その誤解を少しでも晴らしたいという筆者たちの情熱の表れだったことを多くの読者の皆さんに理解して頂きたい。その意味もあって、本稿も当分『秘伝千羽鶴折形』に集中することになる。
『秘伝千羽鶴折形』には、49種の作品の折形図(完成図)と、それぞれの用紙切り方図(また一部は展開図)が描かれているわけだが、その切り方図は、紙の裏を上にして描かれたものである。大部分の折形はどちらであっても関係がないため、これは案外に気が付きにくいことであったが、よく見ると『拾餌えひろい』の切り方図は裏が上であった。試しに表を上にして折ってみると、小鶴が原折形図とは反対の、向かって右側に付いてしまうのが解るだろう。裏を上にした図ならば、ザブトン折りが自然に折れるし、用紙に製図して切り取る場合にも綺麗に仕上げるためには便利である。複製本をそばに置いて見る読者の便を考慮して、解説の方も原本通りにして置いた。従来の同種本がすべて表を上にしているという事情もあって、混乱している向きもあるとのことだが、是非先入観によらず解説の初めの部分から順に読んで頂きたいものである。
用紙に製図するということも実はあまり感心しない。(私は一度も製図して切ったことがない。)すべて折ることだけで作図できるのだ。挿絵などで見るかぎり、当時の人は、紙とハサミだけで作っている。むずかしげな比率が書いてあって、三角定規やコンパスなどで作図しなければならないものという先入観が(特にご婦人方の中に)『千羽鶴』はムズカシイという観念を植え付けてしまったのではなかろうか。3等分が面倒なら4等分にして切り落とせばいい。7等分ならまず8等分に折ればよいのだ。正しく「等分」にする必要がないものも多い。正しく正方形にする必要も実はないのである。だいたいこの程度という感じで折ればよいのだ。折り鶴はゆがんだ紙でも折れるのだ。正しく等分したところで、ツナギ部分を切り残せば、どうせ不正確になってしまう。定規を使わないで作図できるというのが折り紙の魅力のひとつであるということは数学好きの人には常識であろう。しかし数学の嫌いな人達までがなにも一生懸命に幾何のお勉強よろしく難しい作図をすることはないのではないかと思う。
【第六回】
 『秘伝千羽鶴折形』研究史上大きな業績を残された児玉一夫さんが亡くなった。長崎の平和公園に近い医院に入院中の児玉さんをお見舞いしたのは二年前だったが、二日間に二度お会いして、それが最初と最後の機会になってしまった。
『秘伝千羽鶴折形』研究史上大きな業績を残された児玉一夫さんが亡くなった。長崎の平和公園に近い医院に入院中の児玉さんをお見舞いしたのは二年前だったが、二日間に二度お会いして、それが最初と最後の機会になってしまった。
面長の老歌舞伎役者と言った風貌の方で、最近は折り紙に関心が無くなったとおっしゃりながら、なお、昭和六年刊『折紙教本』内山光弘著の原本を見ないと死んでも死にきれないから探してくれという、以前からの依頼事を繰り返し口にされた。幸い同書は、昨年玉川大学に有ることが分かってコピーをお送りして、私としてもホッとしたのであった。
児玉さんは昭和32年11月から『千羽鶴折形』の原本を見たいという念願を起こして、熱心に動き始める。先ず内山・吉沢両氏に手紙を書く。九州各地の図書館に所蔵を問い合わせる。やがて借用は諦めて、購入すべく東京の有名古書店へ連絡を取る。この間のいきさつは丹念に記録されているのだ。昭和33年4月25日付で南陽堂から「・・・不申候・・・」という古文書のごとき葉書が来ている。思いがけず辰巳書店から「・・・当方の目録に記載してあります。代金千円です・・・題箋完備の好い本です・・・」という連絡があり、すぐ送金して現物が到着したのが5月6日、それから「百鶴 出来上り 本書全部完了した」という記載のある9月7日までの四か月間の児玉さんの熱中ぶりは想像に余りある。原文を読むための、変体仮名の勉強から始めて、苦心惨憺しておられる。そして後に笠原氏の解説書のために原本の写真を提供されて、この書の普及に絶大な功績を残されたのであった。
この度、協会の『秘伝千羽鶴折形』解説書を心待ちにしておられたのに、発行が伸び伸びになっている間についに帰らぬ人となられたのは、誠に悔やまれることであった。享年81歳。ご冥福を祈るばかりで言葉もない次第である。
現在、児玉本『秘伝千羽鶴折形』は、私がお預かりしている。この本の特徴は、まず題箋が完全に残っていること。これは天下に2冊しか知られていない。刷りの時期はかなり遅いようで板木の痛みがかなり進んでいること、他の諸本に比べて用紙が一回り大判になっていることなども注意すべき点だが、特に、寛政12年求板本であって、初版本に比べて現存することの確認できる数が極めて少ない(2冊だけ)という価値のある本なのである。初版本の序に押されている3つの印が落ちていることも重要な資料になる。これは吉野屋から板木と版権が小刀屋に売られた時に、編著者籬島の手を離れてしまったことを示していると推定されるが、児玉本以外の他の一本は序の部分を失っているので、求板本がすべて序の三印を欠いていたのかどうか確認できない。しかしながら、三印を完全に欠いている序を持つ本は児玉本が知られているだけなのである。
児玉さんは、『折形手本忠臣蔵』を入手されて、そのコピーを関係者に配布するという、世の好事家たちの為し得ぬ快挙をされた人としても忘れられない。普通はたいがい珍しい資料は人に見せないものなのである。この忠臣蔵の原本は今回の調査で発見出来ず、散佚と認めざるを得ないのは残念なことであった。
【第七回】
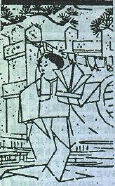 今年も忠臣蔵の季節になった。今回は『折形手本忠臣蔵』について書こうと思う。作者は未詳。ただ、私は津山勇蔵という人物だった可能性を考えている。板元が大坂の小刀屋六兵衛であることは確認出来た。刊行年は寛政12年以後の数年間と推定できる。(『秘伝千羽鶴折形』解説書で吉田正美氏が寛政2年以前としたのは誤りであることが最近判明した。したがってこの稿の【第4回】の記事は訂正したい。)
今年も忠臣蔵の季節になった。今回は『折形手本忠臣蔵』について書こうと思う。作者は未詳。ただ、私は津山勇蔵という人物だった可能性を考えている。板元が大坂の小刀屋六兵衛であることは確認出来た。刊行年は寛政12年以後の数年間と推定できる。(『秘伝千羽鶴折形』解説書で吉田正美氏が寛政2年以前としたのは誤りであることが最近判明した。したがってこの稿の【第4回】の記事は訂正したい。)
『折形手本忠臣蔵』は、内山興正師の名著『折紙』で、不自然な作で紹介する意味も無いように書かれて以来、つまらないものという扱いを受けて来たが、もともと『千羽鶴』などと比較して造形的な批判をすることはあまり意味がない。そもそも折り鶴が傑作なことは言うまでもないことであり、それと比較して劣ると言っても、それだから価値が低いということにはなるまい。
『折形手本忠臣蔵』は、完成図がかなり正確に描かれていて、その点でも『千羽鶴折形』と全く異質である。この折形を楽しむためには、まずその完成図通りに正確に折るように努めることが必要である。そして役者の演技の微妙な息づかいまで表現しようとしている作者の意図もつかんで欲しい。[切り込み]もあり、[ぐらい折り]に徹しているところなどは現代折紙の常識に対してのアンチテーゼともなり得る。ぜひ一度試してみることをお薦めする。
注意点は、雑誌『おりがみ』197号に載っている『かやら草』の[猿猴]と同じ基礎折りを用いること。(ただし4分の3と書いてある切り込み部分を5分の4にする。)
最初の顔世御前からいきなり手に持つ兜を同一紙で折り出すという発想は現代の我々に近い。顔世とその夫の判官を合成したような姿に作ってあるところや打ち掛けを着ていないところなど、[くらいぼし]というメイクアップがしてあるのも現在とは違っている。背景の足利家の紋を間違えているのはご愛嬌である。
顔世の折り方のヒント。(1)途中図は九分通り正確である。(2)右足は中心線に沿って山折りを谷に折り返す。(3)左手は一度開いて、兜と同じ位置で同じように折り始めること。
【第八回】
 『秘伝千羽鶴折形』の挿絵「春遊び図」を見ると、京都の(これは髪形から分かる)良いところの奥さんと、折紙遊びをしている娘たち(振袖を着ている)と男の子と、それを感心しながら見ているらしい使用人(下女)たちが描かれていて、この図で見る限り、当時(18世紀末)折紙は、かなり余裕のある階層の、女性や子供たちの間で享受されていたことになるであろう。果たして実態はどうだったのだろうか。
『秘伝千羽鶴折形』の挿絵「春遊び図」を見ると、京都の(これは髪形から分かる)良いところの奥さんと、折紙遊びをしている娘たち(振袖を着ている)と男の子と、それを感心しながら見ているらしい使用人(下女)たちが描かれていて、この図で見る限り、当時(18世紀末)折紙は、かなり余裕のある階層の、女性や子供たちの間で享受されていたことになるであろう。果たして実態はどうだったのだろうか。
この種の絵でもっとも古いとされる『けいせい折居鶴』(1717刊か)の挿絵では、寺子屋の師匠と弟子(ともに男性)が折っているが、その後に男性が折っている絵のあることを知らない。わずかの間に、折紙は、すっかり「女子供」のものになってしまったのであろうか。
児玉本『折形手本忠臣蔵』の広告欄に出ている『秘伝千羽鶴折形』は「御子達にてもがてん仕安きやう絵図を以て委しくしるす書なり」と書かれているが、これが商売上の宣伝文句にすぎないことはご存じの通りである。しかし、当時折紙が一般に「子供達」のものであるとされていたことが推察され、「子供達にも分かり易い」「図で詳しく説明してある」というのが現代でも重視されている折紙の本の宣伝文句であることを考え合わせると、実態はあまり変わっていなかったのかも知れない。
勿論、『秘伝千羽鶴折形』の作者たちは男性だったが、序文では「青女房、露菊」の作という虚構を用いてとぼけているのは、「土佐日記」のひそみに倣った古典趣味というだけでない、封建的な男尊女卑の思想に支配されていたからであるとされているが、その点では明治以後と同じような実態であったかどうか、疑問もあるのである。
吉沢章氏秘蔵されるところの『五百折箱』は、享保12年に加賀藩の家老が折った折形だそうで、千羽鶴の魯縞庵や「新撰折形図会」の津山勇蔵や、幕末に浅草で焼き塩などを売っていて何でも折紙にして折ったという名人(「嬉遊笑覧」による)など、伝えられている限りの江戸時代の折紙名人は男性であって、女性に仮託されている例も「露菊」以外に聞いたことがない。これは女性が蔑視されていて(ということは折紙が蔑視されていて)女性の名が記録されなかったと説明する論理は生じて来ないのではなかろうか。
© OKAMURA 1990,1991,1992
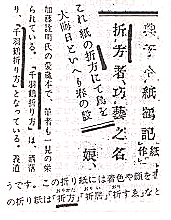 本新聞の「編集人」としての立場から一言お詫びを申し上げるが、前号にはミスプリントが多々あり、汗顔のいたりである。校正の手抜きであったが、中でも『千羽鶴折方』などを見過ごしたのは(*)遺憾であった。
本新聞の「編集人」としての立場から一言お詫びを申し上げるが、前号にはミスプリントが多々あり、汗顔のいたりである。校正の手抜きであったが、中でも『千羽鶴折方』などを見過ごしたのは(*)遺憾であった。
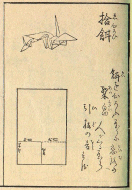 『秘伝千羽鶴折形』という本は、この十数年の間に、折り紙ファン層の中に深く静かに浸透していた。一人でこつこつ折る少年がいるかと思えば、千羽鶴折形研究会を作って研鑽を重ねる熟年者のグループがあったり、その年令性別を問わぬ広がりぶりを考えると、ここにこそ折り紙の魅力とは何かという問題の鍵を見る気持ちがするのである。
ところで、『千羽鶴折形』は、数々の誤解に取り囲まれた不幸な運命の書でもあった。今回のNOAブックスの解説書は、その誤解を少しでも晴らしたいという筆者たちの情熱の表れだったことを多くの読者の皆さんに理解して頂きたい。その意味もあって、本稿も当分『秘伝千羽鶴折形』に集中することになる。
『秘伝千羽鶴折形』という本は、この十数年の間に、折り紙ファン層の中に深く静かに浸透していた。一人でこつこつ折る少年がいるかと思えば、千羽鶴折形研究会を作って研鑽を重ねる熟年者のグループがあったり、その年令性別を問わぬ広がりぶりを考えると、ここにこそ折り紙の魅力とは何かという問題の鍵を見る気持ちがするのである。
ところで、『千羽鶴折形』は、数々の誤解に取り囲まれた不幸な運命の書でもあった。今回のNOAブックスの解説書は、その誤解を少しでも晴らしたいという筆者たちの情熱の表れだったことを多くの読者の皆さんに理解して頂きたい。その意味もあって、本稿も当分『秘伝千羽鶴折形』に集中することになる。 『秘伝千羽鶴折形』研究史上大きな業績を残された児玉一夫さんが亡くなった。長崎の平和公園に近い医院に入院中の児玉さんをお見舞いしたのは二年前だったが、二日間に二度お会いして、それが最初と最後の機会になってしまった。
『秘伝千羽鶴折形』研究史上大きな業績を残された児玉一夫さんが亡くなった。長崎の平和公園に近い医院に入院中の児玉さんをお見舞いしたのは二年前だったが、二日間に二度お会いして、それが最初と最後の機会になってしまった。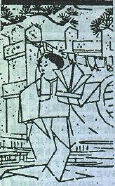 今年も忠臣蔵の季節になった。今回は『折形手本忠臣蔵』について書こうと思う。作者は未詳。ただ、私は津山勇蔵という人物だった可能性を考えている。板元が大坂の小刀屋六兵衛であることは確認出来た。刊行年は寛政12年以後の数年間と推定できる。(『秘伝千羽鶴折形』解説書で吉田正美氏が寛政2年以前としたのは誤りであることが最近判明した。したがってこの稿の【第4回】の記事は訂正したい。)
今年も忠臣蔵の季節になった。今回は『折形手本忠臣蔵』について書こうと思う。作者は未詳。ただ、私は津山勇蔵という人物だった可能性を考えている。板元が大坂の小刀屋六兵衛であることは確認出来た。刊行年は寛政12年以後の数年間と推定できる。(『秘伝千羽鶴折形』解説書で吉田正美氏が寛政2年以前としたのは誤りであることが最近判明した。したがってこの稿の【第4回】の記事は訂正したい。) 『秘伝千羽鶴折形』の挿絵「春遊び図」を見ると、京都の(これは髪形から分かる)良いところの奥さんと、折紙遊びをしている娘たち(振袖を着ている)と男の子と、それを感心しながら見ているらしい使用人(下女)たちが描かれていて、この図で見る限り、当時(18世紀末)折紙は、かなり余裕のある階層の、女性や子供たちの間で享受されていたことになるであろう。果たして実態はどうだったのだろうか。
『秘伝千羽鶴折形』の挿絵「春遊び図」を見ると、京都の(これは髪形から分かる)良いところの奥さんと、折紙遊びをしている娘たち(振袖を着ている)と男の子と、それを感心しながら見ているらしい使用人(下女)たちが描かれていて、この図で見る限り、当時(18世紀末)折紙は、かなり余裕のある階層の、女性や子供たちの間で享受されていたことになるであろう。果たして実態はどうだったのだろうか。