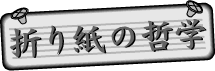第2章 3弁のあやめ
不切正方一枚について
(折紙探偵団新聞第41〜42号)
この章では、「不切正方一枚で折るということ」について考えてみます。ところで、なぜ「正方形で折るということ」ではなく、「はさみを使わないで折るということ」でもなく、「不切正方一枚で折るということ」なのでしょうか。この問題の重要性は、前川淳の「折り紙博物誌第2部(折り紙探偵団新聞第5巻)」で議論されていますので、ここでは簡単に説明します。
不切・正方・一枚
ふつう折り紙を折るためには、まず紙を正方形に切らなければなりません。その正方形の紙から出発して、折るだけで作品をつくれば「不切」、切り込みを入れれば「不切でない」といわれます。しかし、正方形に切る前の紙を出発点と考えれば、私たちは常に紙を「切って」います。また、正方形の紙にあらかじめ切り込みを入れて、その時点を出発点と考えれば、それは「不切」であるということになります。
複合作品についても、複数枚の紙による作品と見ることができると同時に、一枚の紙から出発して、はさみを使ってつくる作品と見ることもできます。このように、「不切」「正方」「一枚」は密接に結びついていて、分けて考えることはできないのです。
3弁のあやめ
例えば伝承作品の『あやめ』を考えてみましょう。実際のあやめは3弁ですが、折り紙のあやめは4弁です。そこで、3弁のあやめを折ることを考えてみましょう。
まず、正3角形の紙を使えば3弁のあやめを折ることができます。ところが、実際折ってみると、バランスが違ってしまい、伝承のあやめの持っている雰囲気を失ってしまいます(図1)。これでは、あやめではなくて別の作品になってしまいます。
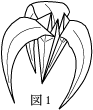
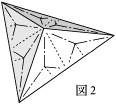
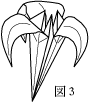
本来のあやめの角の配置や角度を保ちつつ、しかも3弁にする方法があります。平面の紙から出発するのではなく、図2のような、3角錐の側面の形をした紙から出発すれば、伝承のあやめと全く同じプロポーションをした、3弁のあやめができます(図3)。
不切正方一枚のあやめ
これでは「折り紙」らしくないと感じる人もいるでしょう。それはきっと、出発の時点ですでに紙が立体になっているからでしょう。それなら、正方形の紙から出発して、折るだけで図2の形をつくることができるとしたらどうでしょう。実際、正方基本形の角を1つ折り込むことによってそれは可能です(図4)。こうすると、何やら「折り紙」らしくなってきます。
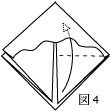
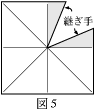
まとめ
3弁のあやめを不切正方一枚で折ることは可能ですが、この場合、紙の多くの部分を無駄にしていることになります。そればかりか、ある部分は作品を折りにくくするためだけに使われています。3弁のあやめを折る際に、正方形から出発する必然性はなく、むしろ図2の紙から出発することに必然性があります。もし、図2の紙から出発する作品は折り紙とはいえないと考えるなら、そして不切正方一枚による3弁のあやめは不切正方一枚であるがゆえに折り紙であると考えるなら、それは本来折り紙ではないものを無理矢理折り紙にしたといわれなければなりません。不切正方一枚であるからといって、すべてが折り紙であるとは限らないかもしれないのです。
『牛』と不切正方一枚
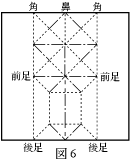 もう1つ似た例を出しましょう。図6は、内山興正の『牛』の展開図です。この作品の折り図は『をる』の第15号に掲載されていて、それによると不切正方一枚になっています。ところが、展開図からお分かりの通り、すべてのカドは1対2の長方形の中から折り出されています。折り図では最初に観音折りをしているのですが、この操作は全く余計で、単に紙を重ねて折りにくくしているだけです。
もう1つ似た例を出しましょう。図6は、内山興正の『牛』の展開図です。この作品の折り図は『をる』の第15号に掲載されていて、それによると不切正方一枚になっています。ところが、展開図からお分かりの通り、すべてのカドは1対2の長方形の中から折り出されています。折り図では最初に観音折りをしているのですが、この操作は全く余計で、単に紙を重ねて折りにくくしているだけです。
さて、「折り紙は不切正方一枚でなければならない」といわれることがあります。そうだとすると、この『牛』は折り紙なのでしょうか。
ここで、少なくとも2つの選択肢があります。第1に、『牛』は本来不切正方一枚ではないので、折り紙ではないとする立場、第2に、『牛』は不切正方一枚であるので、折り紙であるという立場です。ところが、どちらの選択肢を選んでも、問題が生じるのです。
不切正方一枚と折り紙
まず、後者の立場について考えてみましょう。この場合、「折り紙は不切正方一枚でなければならない」という条件は、その見かけとは裏腹に、とても弱いものになります。例えば、ロバート・ラングの『鳩時計』は1対10の長方形から、デビット・ブリルの『馬』は正3角形から折ることになっていますが、どちらも不切正方一枚で折ることが可能です。したがって、これらの作品は不切正方一枚であることになり、それ故に折り紙であるということになります。
「折り紙は不切正方一枚でなければならない」という主張は、それだけでは、あまりに多くを許容してしまいます。これでは、なにか意味のある主張をした気にはなりません。そこで、第1の選択肢を選びたい気がしてきます。「不切正方一枚」には、文字どおりの意味の他に、例えば「形をつくるのに貢献していない部分は除いて考える」という条件が含まれていると考えることができます。こうすれば、主張の威力を強くすることができます。
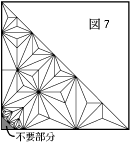
しかし、今度は強すぎるのです。これでは、あまりに多くを排除してしまいます。一般に不切正方一枚だと思われている作品のすべてが、本当に正方形のすべてを無駄なく使っているわけではありません。前川淳の『悪魔』にさえ、わずかですが無駄な部分があります(図7)。このような無駄な部分を全く許さないとしたら、不切正方一枚である作品は本当に少なくなります。
折り紙批評に向けて
「折り紙は不切正方一枚でなければならない」といったとき、「不切正方一枚」の規準が問われなければなりません。ある作品が不切正方一枚であるかどうかは、形式的に決まるものではなく、解釈する人による程度の差が入り込む余地があります。そうであるならば、私たちは第3の選択肢をとるべきでしょう。すなわち、『牛』が折り紙であるかどうかは、それが不切正方一枚であるかどうかとは別の規準によって決められるべきだという立場です。
一般に、折り紙について議論するとき、それが形式的に不切正方一枚の規準を満たしているかどうかはあまり意味がありません。それぞれの作品について、どんな紙を使い、どのように折って、どのようなものになるか、総合した判断を下す必要があります。私たちは、個々の作品の「内容」にいちいち入ってゆかなければなりません。そして、この点にこそ折り紙批評の生まれる余地があるのです。
補遺
折り紙にとって不切正方一枚という概念が重要だというのは、私の考えでは、全くの謬見です。折り紙をパズルと考え、パズルのルールとして不切正方一枚という概念をとらえる考え方もありますが、もとよりパズルのルールは恣意的に決めることができるもので、折り紙のルールが不切正方一枚である必然性はありません。実際、江戸時代の折り紙には、長方形の紙に切り込みを入れたり、六角形の紙を使ったりするものが多くありますし、その中にはパズルとしてみても面白いものが少なくありません。
おそらく、あらかじめ正方形に切られた紙が折り紙用紙として売られているということが、不切正方一枚に対する「信仰」を生んだのでしょう。
![[home]](../../../global/ToHome.gif)
![[第1章]](../../../global/Left.gif)
![[back]](../../../global/Up.gif)
![[第3章]](../../../global/Right.gif)